山口百恵さんのファイナルコンサートの録画ビデオ視聴。
去年の10月にNHKのBSで放送された際に録画したものを、今頃になって視聴。
マイクを舞台上に置いて消えていった、あの伝説のコンサートです。
テレビで1~2曲歌う姿しか見たことがなかったので、ちょっと唖然としました。
何だろう、この存在感。とても21才とは思えない、凜とした佇まい。
周囲がなんと言おうとも、自分で自分の幸せをつかもうとする強さ。自分自身を貫く潔さ。
そんなのが全て、コンサートにギュッと詰まってました。
それに、なんて歌が上手なんだろう。
うちの両親、いったい彼女のどこを見ていたんだろう。
彼女がデビューしたのは、私が小学生の時。
デビュー初期は、当時としては、なかなか刺激的な歌詞の歌を歌っていたし、年齢にしては大人っぽい雰囲気だったこともあって、「こども=かわいい」という価値観を持つ両親は、百恵さんのことが気に入らなかったようです。
レコードを売るための戦略であって、決して彼女のせいではないのにね。
歌が下手だ、若いのにかわいげがないと、テレビで見るたびにふたりは言い続けてました。
「秋桜」あたりから、特に母は曲の良さを認め始めましたが、彼女への評価は変わらなかった。
特に十代前半の頃は、家庭環境がちょっといろいろアレだったので、自分自身の保身のために、親の好みに日和りがちだった私。
彼女に興味を持つべきではないと、自分を押さえつけていたんだろうなと、今は思います。
芸能生活、たった8年だったんだ。本当に、絶頂期に、引退してしまったんだ。
そりゃあ、伝説になるよなあって、思い知らされました。
指揮者がいる生バンド(指揮は服部克久さん!)、ファイナルコンサートとは思えない地味なライティング、お行儀のよい観客たち。
40年以上前の昭和の時代感も楽しめました。
「天気の子」の録画ビデオ視聴。
今年初め、地上波で放送された際に録画したものを、今頃になって視聴。
「天気の子」というタイトルからは、映画の内容が予想できなかったので、興味が持てるかどうか不安だったのですが、社会現象になるくらいの大ヒット作だから、きっと大丈夫だろうと思い、録画しておいたものです。
まずびっくりしたのが、ディテールの細かさ。
町の様子、店や商品名などの名称も、そのまま使われ、丁寧に再現されているのにもびっくり。まるで絵のようだと感じる風景もありました。
Yahoo!知恵袋が何度も登場するのも、面白かった。ああ、若い子はこんな使い方をしてるんだなって。
それと、スピード感。
最近のドラマは、私には展開が早すぎて、置いてけぼりされてしまうものも多いのですが、この映画は、何の予備知識もない私でも、内容についていくことができました。
声の出演者も、しっかりした俳優さんが脇を固められていたせいか、違和感がありませんでした。
何か、ジブリ作品のような香りがするなあ。
見終わって、陽菜を帆高が連れ帰るという選択は、ふたりにとって、世界にとって、正しかったのかな、でも、正しさを問うなんてことはできないのかな、などと感じました。
RADWIMPSの「愛にできることはまだあるかい」、映画と共に聴くと、余計に染みますね。
オリンピックの開会式を視聴。
オリンピックの開会式の生放送を、最初から最後まで見続けたのは、たぶん生まれて初めてだと思います。
長時間ではありましたが、とても楽しめました。選手たちがスマホを持ち、うれしそうに撮影しているのも時代なあと感じつつ、楽しそうで微笑ましかった。
誰かさんの挨拶が異常に長かったこと以外は、ね。
オリンピック、本当にできるのかなとは思っていましたし、呆れるような出来事もたくさんありました。オリンピックが終わっても、山積した問題が消えるわけではありません。
でも、オリンピック出場に人生を賭け、文字通り、血がにじむような努力を日々続ける人が、世界中にたくさんいる。
大会を成功させるため、陰に日向に、できうる限りの準備を誠意を持って進めていた人も、きっとたくさんいる。
そういう人たちは、きっと抱えきれないほどの不安を抱きつつ、この日を迎えたんだろうなと想像すると、言葉にしがたい感情がこみ上げました。
頑張ってきた人たちの努力が報われる大会になりますように。

「よつばと!」を楽しむ。
親戚から「鬼滅の刃」を借りた時、他にも漫画を数作貸してくれたのですが、その中で一番面白いと感じたのが 「SPY×FAMILY」。
返却時にそう言いますと、「それならこれも面白いと感じるかも」とあらたに貸してくれたのが、 「よつばと!」 です。
よつばちゃんと、周囲の大人たちの、何でもない日常を綴った漫画ですが、確かに面白い。
よつばちゃんが繰り出すヘンテコな言葉が、もう何ともたまらんですが、一番いいなあと思うのが、 登場人物たちの距離感です。
よつばちゃんの出自など、登場人物についてはわからないことが多いです。でも誰も気にしていないし、余計なことも聞かない。
みんながみんな、あるがままを受けいれている。
奇妙な日本語を自在に操り、いろいろな失敗をしでかしつつ、よつばちゃんは今日もきっと、ご機嫌に暮らしていることでしょう。
何でもない日常って、とても愉快で、とても大切なもの。
そんなことをじんわり教えてくれる作品だなと感じます。
既刊読破まで、あと数冊。
私が突然変な声で笑い出し、たまたま横にいたダンナをびっくりさせたものですから、彼とはソーシャルディスタンスを保って読み進めてます。











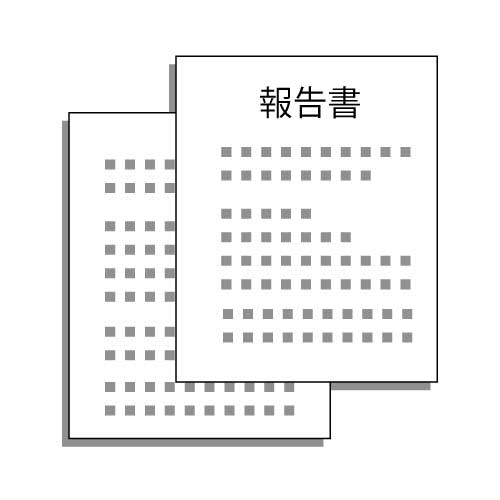





コメント